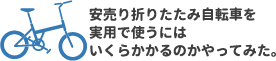前回の記事で、
リムを計測すると、結構細身のタイヤでも入りそうなので、交換してみました。
交換するタイヤはいつもの通り安物タイヤです。
DURO(デューロ) DB-7023 Rollover 20×1.35 160-01611 1,109円(安っ)
もちろんスチールビードです。

ロゴ入りです。
ロゴ入りのタイヤは、なんか高級っぽいですね。


「Puncture Protection」パンクしにくいのでしょうか?
商品説明によると、「トレッド下に配置したスペシャルレイヤー(特殊層)が、トレッドの剛性を高めることでコーナーリングやブレーキングの際のタイヤ形状を維持し、パンクを抑制」するそうです。

タイヤのサイドは柔らかいです。

前輪はサクッと交換しました。
大分慣れてきて、15分程で交換し終えます。

取り外したタイヤと並べてみました。

左:20×1.75(ETRTO:47-406)から、右:20×1.35(ETRTO:35-406)へ交換、かなり細くなっています。
本当なら、チューブも交換しなくてはならないのですが、とりあえずそのまま使っています。
検索でも「タイヤ交換」のキーワードが上位にくるので、私なりのタイヤ交換を説明しておきます。
(どうやら私の交換方法は、特異な交換方法のようです。自己流なので参考程度にしてください。
パナソニックのタイヤ交換方法「Panaracer 補修用自転車タイヤ 取扱説明書」とは、全く違います。)
タイヤ交換の注意点は一つ、チューブを傷つけないにつきます。
コツとしては、常にチューブにエアを少し残しておくことです。
チューブにエアを少し残すことで、チューブがタイヤ側に寄るので、リム近くからチューブを離してタイヤレバー等でチューブを傷つける確率を減らします。
まず、タイヤを外します。
この時も、エアを全部抜かずに、少しだけ残しておきます。
バルブのリムナットは、緩めておきます。

タイヤを揉むようにして、タイヤのビードをリムからはがします。

バルブと対角側に、タイヤレバーをかけます。
タイヤレバーは、チューブを傷つけないようにビードだけに掛けるように、深く入れすぎないように。

最初に掛けたタイヤレバーの左右にもタイヤレバーを掛けます。
左右にタイヤレバーを掛けると、最初のタイヤレバーが勝手に外れます。

外れた部分に指をかけて、リムからタイヤを取り外します。
この時に反対の手でタイヤを、上から軽く押しつぶしながら外すと、外しやすいです。

チューブをリムに挟まないように注意しながら、残ったビードをリムから外します。


バルブのリムナットと袋ナットを外して、バルブをリムから抜き取ります。

タイヤとチューブが取り外せました。

タイヤをはめます。
タイヤの中に、チューブを入れます。
適当で大丈です。

一度チューブにエアを軽く入れて、チューブのねじれや片寄りをとります。
この時に、チューブに穴が空いていないか確かめておきます。

エアを抜いて、バルブをリムのバルブ穴に入れて、リムナットを仮止めします。

タイヤの片側のビードをリムに入れて、バルブの位置を合わせます。


エアを少しだけ入れます。
バルブの部分からタイヤのビードをリムに入れていきます。
タイヤのビードが入れにくいようなら、エアを少し抜いて、タイヤのビードがリムにはまるギリギリのエアを残します。

タイヤのビードをリムに入れるのがきつくなったら、リムとタイヤの間にチューブを挟まないように注意してください。

このタイヤはサイドが柔らかかったので、手で入れました。
エアが入りすぎていると入りません、チューブにほんの少しエアが残っていれば、チューブがリム側に落ちてこないので、リムとビードにチューブをはさんでパンクさせる確率は減ります。
エアを適度に抜き少しだけチューブにエアを残し作業してください。
チューブラータイヤ乗りの、オールドレーサーの方ならば、この柔らかなタイヤならタイヤレバー無しで入れられます。
文字で表現するのは難しいですが、タイヤの左右を持って、タイヤを上に伸ばすように入れるとパコッと入ります。

タイヤレバーを使うときには特に注意してください。
一度にタイヤを入れようとせず、少しずつ入れていくようにすると、タイヤレバーでチューブを傷つけにくいです。
タイヤに少しエアを入れて、タイヤに少し力を加えて転がして、タイヤとチューブをリムになじませます。
タイヤのリムラインが全周ににわたり均一に出ていることを確認してください。
※参考「パナレーサー タイヤのリムラインの調整方法」

タイヤが細くなったことで、シャープになりました。
泥除け戸の隙間も大きくなりました。
意外と乗り心地もゴツゴツしていません。
漕ぎ出しは非常に軽くなりました。
ただし、コーナリングは若干不安定になりました。
小径車の細身のタイヤは、結構コーナリングがシビアですね。
慣れれば問題ないでしょうが、ちょっと注意が必要ですね。
街乗りなら、このサイズ(20×1.35)までが適正じゃないでしょうか、これ以上細いと低速域の安定感が損なわれると思うので、気軽に乗るにはこのサイズまででしょうね。
あとは、英式バルブのママチャリチューブが、どこまで持つのか不安ではあります。
最後にサイクルコンピューターのタイヤ周長を設定します。
47-406 20X1.75 1,515mm(152cm)
35-406 20×1.35 1,460mm(146cm)
参考「CATEYE タイヤ周長ガイド」
カセット式ボトムブラケットを入れたときからですが、タイヤを細くしたことで、ますます6速でも踏み切ってしまいます。
「DNP 11T-28T ボスフリー 7段ギア SHIMANO(シマノ) MF-HG50-7 互換 LY-1107KFN (7速 11-28T)」で、7速化してトップを11Tにする構想も膨らんできました。
DNPのボスフリーギアは、SHIMANOでは絶滅した11Tギアを採用しています。
6速 MF-TZ20 14-28T(14-16-18-21-24-28T) ※現在付いているリアスプロケット
DNP 11T-28T ボスフリー 7段ギア (11-13-15-18-21-24-28T)
11Tがトップ側に追加されて、6~5速が1枚歯が少ないです。
6速までは、今までと同様に使えて、7速に11Tでオーバートップが追加されるようなイメージですね。
ディレイラーは今のままで使えるはずなので、シフターを7速用(「シマノ サムシフターPLUS リア7S インデックス SL-TX30-R7 ASLTX30R7AT ブラック」)に、交換すれば大丈夫そうです。
問題はフレームとのクリアランスです、7速ギアは当然6速ギアよりも幅が増しますので、フレームなどに干渉する可能性はあります。
また、人柱になってみますかねぇ・・・。

後日、7速化しました。
ディレイラーがRD-TZ50でも7速化はできたのですが、ディレイラーをALTUS(RD-M310)に交換しました。
変速のスムーズさはALTUS(RD-M310)とは雲泥の差でした。
7速化は工夫が必要なのと、バンドブレーキからキャリパーブレーキへと交換しないとフレームのエンド幅に収まらない可能性もあります。
万人向けではありませんが、チャレンジ精神旺盛な方であれば、工夫次第でできると思います。
(不器用な私でもできましたから。)
今回の出費
部品
DURO(デューロ) DB-7023 Rollover 20×1.35 160-01611 1,109円x2本
———————————-
計 2,218円
工具
0円
———————————————–
計 0円
今回の合計 2,218円
トータルの出費 48,025円 (部品 41,310円/工具 6,715円)